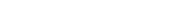![中田ヤスタカさん × 平澤創 [対談]](/25th/images/dialogue/sp_talk/09/09_bb_bg.jpg)
![中田ヤスタカさん × 平澤創 [対談]](/25th/images/dialogue/sp_talk/09/09_bb.png)
フェイス25周年記念Webサイトスペシャル対談企画8
心を動かされるのは、初めてに出逢うとき。
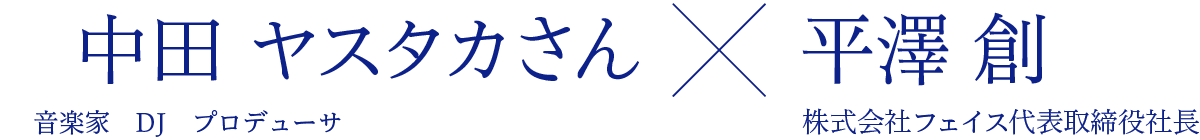
バンドやシンガーでなくても、
音楽で表に立つ職業もある。
音楽で表に立つ職業もある。
平澤
フェイス・グループ25周年記念対談にお越しいただきありがとうございます。昼間にお会いするのは初めてかもしれませんね。
中田
そうかもしれませんね。お酒を1杯も飲んでいない(笑)。
平澤
本当に(笑)。そういえば、私も中田さんのことを「王子」って呼ぶけど、何で「王子」って呼ばれているの?
中田
わからないです。デビューしたての頃にマネジメントをしている人に最初に言われたんですが、すごく生意気、わがままに思われていたのかもしれないですね。一人でずっと曲を作っていたので、いざ人と接する時に、結構ストレートな言い方になりすぎていたのかもしれません。もう付き合いが古い人しかそう呼ばないですけどね。
平澤
でも、ここからはいつもの通り「王子」で話しを続けていきますね。今回、王子を是非お呼びしたいと思ったのは、昨年、NHKで放送された「ここから」(2017年11月23日放送)に出演されていたのを拝見して、音楽のルーツ、その成り立ちに非常に興味を持ったからです。
中田
そうなんですか。
平澤
まずは音楽との出会いから伺ってもいいですか。
中田
最初の出会いは、ピアノ教室に通ったことです。姉が通っていたところに、「今週からあなたも行くのよ」と。
平澤
それは何歳の頃?
中田
小学校に入るかどうかくらいですかね。
平澤
気づいたら「ピアノ教室に行くのは普通」という感覚でしたか。
中田
でも、あまりピアノ教室が好きじゃなかったのと、合唱コンクールでピアノ弾かされる役割にはなりたくなくて、学校では公言していませんでした。
平澤
そうなんですか。その後は?
中田
音楽に対する自我が目覚めた最初は作曲ではなく、「デザエモン」というゲーム(内蔵された独自のツールを使って、音楽やグラフィックなどを製作して楽しむシューティングゲーム)を作るソフトでゲーム自体を作り始めたところからです。まだ、任天堂のファミコンソフト「マリオペイント」も発売される前、チップチューン(PCや家庭用ゲーム機搭載の内蔵音源チップで音楽を鳴らす)という言葉もなかった頃のことです。絵を描いたり、工作したりという子どもの遊びの一環というか、でもピアノをやっていたこともあってどんどんハマっていって。そうこうしているうちに、打ち込み機材やMTR(マルチトラックレコーダー)を買って、中学生になると今では死語になったいわゆる「宅録」をやっていました。

平澤
なるほどね。打ち込みした音楽をオーディションに応募したりしたんですか。
中田
中学生の頃から機材欲しさ、賞金欲しさで応募したりしていました。高校生の時には、ヤマハのコンテストにも送りましたけど、デビューはあまり考えてなくて、相変わらず賞金稼ぎの要素が強かった。今だったらYouTubeに曲を上げてお小遣い稼ぐみたいな、そういう発想でした。だから、「プロを目指すなら人を紹介するよ」と言ってくれた方が現れなかったら、多分、そのままだったと思いますね。
平澤
なるほど。音楽で食べていきたいと思うようになったのはいつ頃ですか。
中田
僕はかなり遅かったです。しかも音楽と言っても、効果音を作る人とかで、最終的にはパソコンとスピーカーの前に座ってできる仕事がいいなと思っていました。音楽でデビューというと、ミュージシャンになる、すなわち「人前で披露する」という意味合いが強いじゃないですか。でも、ミュージャンになりたいという感じではなかった。漫画家のように机で作っている時が楽しいという仕事がいいというか、演奏は人前で作品を作れという感覚だから、そこに違和感があったんです。ある年頃になって、DJとかクラブ音楽に触れるようになって、ライブハウスで作った曲を披露するバンドやシンガーでなくても、DJで曲をかけるという方法で表に立つ職業もあるんだ、と気づいたんです。それで、自分で作った曲を、当時はすごく高価でしたけど、10枚だけレコードカットしてもらったり、CD も業者に頼んで焼いてもらったりしたんです。そうしてDJとして作った曲をかけることができるようになるか、ならないか、というあたりから「デビューしたいな」と思い始めました。
技術の進歩と音楽の進歩が
一致しない時代。
一致しない時代。
平澤
デビュー当時は、どんなことを考えていたんですか。
中田
デビューの頃は、「プロ」ということに縛られすぎていて、テレビで見たことのある分業で音楽を作るという仕組みが、本当につまらなかった。でも「メジャーデビューってそういうものなのかな」と受け入れていた、それが最初の頃です。
平澤
なるほど。メジャーでの音楽の作り方が、それまでの打ち込みによる制作とギャップがあった。
中田
そうですね。趣味で音楽を作っていた頃は、機材の進歩が個人的な創作活動を後押ししてくれていたので、特に学生の時は、一人でできる範囲が広がっていく楽しみがありました。新しい機材に入れ替えたり、増やしたりすることで「この環境だとこのサウンドが限界」といった物理的な問題を解決できる可能性が広がっていった。でも、僕がプロになった時、すでにアシスタント・エンジニアやパンチングする人を必要とする分業で音楽を作るというシチュエーションはなくなりつつあったのに、まだその古い体制の中に身を置いて曲を作ることにすごく違和感があって。デビュー後4、5年は、それを自分一人で音楽を作り込むという元の制作スタイルに戻す作業をずっとやっていた感じです。
平澤
なるほどね。私も一人で曲を作っていた状態からスタジオに入ったけど、当時は、ノンリニア(編集)のハードディスクレコーダーじゃなくて、PCM-3324とかオープンリールのデジタルレコーダーだったから、アシスタント・エンジニアは絶対必要だった。

中田
そうですね。ロケーターする人ですよね。
平澤
うん。そうそう。それが今はもういらない。下手したらスタジオもいらない、みたいな。
中田
そうなっていますよね。
平澤
音楽が進歩していくことと、技術の進歩とが必ずしも一致しない中で、これからの音楽制作の楽しみってどうなると思いますか。
中田
うーん。セッションがしたい人にとっては、楽しみは減っているかもしれないですね。でもクリエイターとして、僕的にはより理想に近づいている感覚ではあるんですよね。
平澤
作り込んでいける。
中田
そうですね。例えば、僕はボカロ(ボーカロイド:ヤマハが開発した音声合成技術。「初音ミク」で一躍脚光を浴びる)はやっていませんけど、ボカロがあることで単純に女友達がいないから女の子に歌ってもらうのは不可能、という限界を突破しましたよね。同じような意味で、頼む人間がいなくてもアイデアを実行できる環境がある、だったらやってみようかなと思う人も確実に増えたと思うんです。
平澤
確かに。形が変わっただけで、クリエイティブな感覚は一緒なのかもしれないですね。
クラブミュージックには
多様な機能性が必要。
多様な機能性が必要。
平澤
初めてヒットしたなという実感というか、「ああ、これが俺だな」と自分の中で感じた、きっかけになった曲とかありますか。
中田
うーん。今のスタイルで行こうというのが明確になったのは、音楽ユニットCAPSULEの6枚目のアルバム「L.D.K. Lounge Designers Killer」と7枚目の「FRUITS CLiPPER」の間くらいでサウンドが見えたんです。ちょうど「L.D.K.」を作っている途中ですでに世に出ていく曲の収録も決まっていたので、次の「FRUITS CLiPPER」で振り切った。「自分の環境じゃないと出せない、他のプロには絶対に無理だろうという音は今これです」と。その時代のプロが初めて許される環境のいい例を出せたなという意味ではそこですね。
平澤
なるほど。少し別の観点から聞くと、これから日本もクラブ音楽やDJも含め、新しい音楽の楽しみ方が生まれて多様性が増していく中で、自分が作曲した音楽にいろいろなバージョンが出てくることは許容できる?
中田
リミックスとか、ミックスとかに対して?
平澤
そうそう。
中田
クラブミュージックは、そもそもオリジナルで知ることが少なくなってきているので、クラブミュージックで言えばそうですね。ポップスとして考えるとちょっとわからないですね。
平澤
うん。
中田
コンサートではオリジナルの方がいいけど、DJブースでは、オリジナルをかけても機能的じゃなかったりする。だから機能という意味では、いろいろなバリエーションが必要になってくると思うんです。機能性は場によって違うので、僕も自分の曲をそのままかけないことも多いですし。
平澤
他のエッセンスも入れるでしょ、いつも。
中田
そうですね、いろいろ混ぜたりとか。やっぱり現場、現場で必要なものも違ったりしますし。例えば、YouTubeでパッと聴く時には、いきなり始まって欲しい音楽でも、DJで使う時には、前の曲と後ろの曲との繋ぎを意識することが多くなる。だから、クラブミュージックとして考えれば、いいと思いますけどね。
平澤
作曲している時と、クラブミュージックと、感覚は全然違うんですか。
中田
自分の中の一つの選択肢であって、それが大きい時もあれば、少なくなる時もある。小さい頃から、その割合は変化しながらも、どちらかが無くなることはないという感じですね。

平澤
なるほど。クラブミュージックというジャンルには、いつから興味を?
中田
最初はテクノですね。「一人で曲を作る=シンセサイザー」といった時代だったので、どんな人がシンセサイザーを使ってどんな音楽を作っているんだろうと調べたら、当時は若い人がテクノを作っていたという感じでした。
平澤
それは何歳の頃?
中田
中学校から高校にかけてです。高校に入るとハウスとかドラムベースとか、聴くものが増えました。
平澤
じゃあ80年代、いや、90年代だ。
中田
そうですね。92、93、94年が中学時代ですね。
平澤
ちょうど、フェイスが創業した時分、92年設立だから。まだインターネットがない時代。
中田
92年、そうですね。
平澤
ちょうどあの頃、こうしたRolandやAKAIのサンプラーで音源を作っていました。
中田
あの時代のことですごく不思議なことがあるんですけど。当時、流行っていたユーロビートをカットアップしながらのメガ・ミックスCDがいっぱいあったじゃないですか。今だと、タブで並べて、パパパパパってできますけど、あの頃はどう考えても無理ですよね。どうやっていたんだろうって。いちいち曲の終わりと頭をサンプリングしてMIDI(Musical Instruments Digital Interface 電子楽器同士を接続するための世界共通規格)で叩いて繋いでって、そういうことやっていたのかな、って。
平澤
そうそう。そういうこと。
中田
すごく大変だなって(笑)。
平澤
そう。すごく大変。かなりお金もかかったし。
中田
そうですよね。
平澤
今なら簡単にできるけどね。
中田
パパッと。
平澤
パパッとできる。あの頃は、ちょうど全部が過渡期の時代ですね。
アナログ制作とデジタル制作の
両方の感性を持つ最後の世代。
両方の感性を持つ最後の世代。
平澤
王子は私と年齢がほぼ一回り違うと思うんだけど、何年生まれ?
中田
僕は申年、80年生まれですね。
平澤
ほぼ一回り違うから、きっと機材に関する経験が違うよね。例えば、この75(Roland S750)とか、新品じゃなくて中古で買ったでしょ。
中田
本当は(AKAI)S3200が欲しかったんですけど、買えなくて、76の中古を買った気がします。
平澤
Roland も55(S550)から75(S750)、76 (S760)になって。
中田
値段もどんどん安くなってきた。
平澤
そうそう。私はスーパーファミコンが発売された年、任天堂のマリオのサウンドチームにいて、この一番高い機材を使っていた。王子は、全体がこなれてきた頃に打ち込みをされていたのかな、と。
中田
僕、さっき知ったんですけど、スーパーファミコン用の3Dシューティングゲーム「Star Fox(スターフォックス)」、僕あの曲、すごく好きだったんですよ。あの曲、平澤さんが作ったんですか。
平澤
そう。任天堂にいた時ね(笑)。
中田
オープニングタイトル後、コマンドAかBを選ぶ時、アレンジバージョンでちょっと静かになるじゃないですか。あれ、めっちゃ好きなんです。同じモチーフでアレンジしてどんどん変えて聴かせる、うわぁと思って。すごく勉強になりました。
平澤
よく覚えていてくれていますね。そうなんですよ、同じモチーフでどんどん聴かせる。
中田
ですよね。落ちサビ(最後のサビの前に挿入される、楽器の音量を極端に落としてボーカルを目立たせたサビ)的な。
平澤
そうそう。聴いてくださってありがとうございます。
中田
すごく印象的でした。
平澤
私は、オーケストレーション(管弦楽法:音楽上のアイデアを、最も合理的かつ効果的な方法で管弦楽団で表現する手段を深く研究する学問)をやっていたんですが、あのゲームは8音の世界の中で、オーケストラに聴こえるようにするのは、結構難しいアレンジが必要なんです。打ち込みでも実際、スコア見たら分かるけど、同時に鳴っているのが少ない。同時に鳴るなら、オケヒット(オーケストラル・ヒット:サンプリング音源の1つ)とかでごまかしも効くんだけどね。細かい音符でうまくオーケストラに聴こえるようにしたのが「Star Fox」なんです。

中田
ああ、ずれてちょっとずつみたいな。
平澤
そうそう、そういうことです。王子はアナログの部分とデジタルの部分の両方を持っていらっしゃる人で、多分、私がやっていた音楽の作り方とか機材の使い手としての最後の世代なんだろうな、と感じたんです。以降の世代って、もう完全にデジタル。
中田
そうですね。
平澤
声すら素材だし。何かこう、ちょっと違う気がする。
中田
そうですね。パソコンで曲を作ることが、すでに一つのジャンルではないと捉えていること自体が大きく違うところだと思います。今は、バンドマンでもとりあえず、シーケンサを買いますけど、以前はパソコンを使って音楽を作っていたグループと楽器を演奏して作っていたグループにはっきり分かれていた。だから、ギターやドラムを持っている人が自分の曲を作ろうかなという時にシーケンサみたいなものを用意するところにすごく違いを感じます。もうデジタル機器というイメージではなく使っているんだろうな、と。
平澤
今では誰でもアプリや廉価なデジタル機器で音楽を手軽に作れるからね。
中田
そうですね。
平澤
その後の世代は、全部打ち込みで、生の楽器の要素ってほぼないよね。
中田
ライブラリを使うという感じに変わっていますよね。
平澤
音素材として、でしょ。
中田
例えばキックの音も、どのバスドラムを叩いているとか、どの機械を使っているかとか、知らないままに音を探して選んでいる感じ。何ていうのかな、波形ファイルでいきなり音が鳴るので。例えば、「Alesisのドラムマシンのキックにゲートリバーブをちょっとかけて、コンプをキツめにかけたパワーキック」みたいな、そういう音、僕らは聴いたら作り方がわかるじゃないですか。元の機材からその音になるまでを逆算できるけど、今の世代は、多分、「そういう音」としてしか、聴いていない。
平澤
なるほど。確かにそうですね。私もエフェクターとかは、結構売ってしまったけど、素材は残している。だけど、今はもう本当に、曲そのものが使えるからね。メモリもそうですし。
中田
そうですね。
平澤
絶対にフロッピーディスクとか知らないよね。
中田
ああ。フロッピーディスク。今の人たちは触ったことないかもしれないですよ。
平澤
そう、多分、触ったことないよね。3.5インチサイズの2HDで1.2MBのものが1枚100円くらいだったけど、今、考えたらありえないよね。
中田
確かに。
平澤
とんでもない容量。「着メロ」って聞いたことあると思うけど。
中田
はい。打ったりしていました。
平澤
うん。最初は2音とか3音だったのが、16音になって、いろんな音ができるようになって。あれ1曲のだいたい容量は2MBで、GM(General MIDI)で128音入っているの、ドラムセットと。私たちが2MBに入るようにサンプリングしていたんだけど。今、2MBなんて言ったら1音くらい、下手したらキックの音一つくらいの容量。
中田
そうですね。iPhoneの写真1枚より少ないくらいですかね。
平澤
さっき言っていたような、音の素材をいかに作っていくのかを、今の人たちは、ほとんど知らない間にやっているのかなという気がする。
中田
そうですね。時系列をまったく気にしなくなってきていると思います。これの後にこれがあって、これの後にこれがあって、1個前、2個前みたいなことじゃなくて、もう全部が古い、みたいな。その全部古いという幅がどんどん増えている。機材に関して言えば、「新発売ヤマハDX音源」とかも、オリジナルの発売日とは違う時系列で出てきたりするので、「新しくこれ出たんだ!使ってみよう」というのと、機材の進歩が一致していないというか。選ぶ側の感覚としては、これまで通っていないものの方が、ある意味、自由に選べるなとも思います。
平澤
最近、新発売でワクワクしたことありますか?昔は、新しいものが出たら欲しいという衝動があったけど。今、楽器とか、音楽系でモノとして欲しいものってあります?
中田
作りたいものはあるけど、売っているレベルでとなると、まあ、ないですね。より快適性を求める方向ではあっても、革新性の方向ではないですよね。確かに進歩ではあるけれど、革命ではないというか。誰もがもう少しこうしたほうがいいと思っていて、でも実現不可能といった世界観は、すごく減っていると思うんですよ。

平澤
確かに。特にモノに関してはワクワク感とか、今はすごく少なくなっていますね。
メディア軸で考えるのではなく、
クリエイティブ・マインドを固定させれば、
選択肢は自然と変わっていく。
クリエイティブ・マインドを固定させれば、
選択肢は自然と変わっていく。
平澤
今、音楽制作の最先端にいる立場から、これからの音楽をどう見ているのか、すごく興味があります。
中田
それは何歳くらいの人に向けて発信するかによって、変わってくる話だと思うんです。例えば、過去に自分が「これはすごい」と思ったもの、例えば、「うわ、この映像すごい」と思う基準、「こういった設定、初めて見た!」という気づきは、最初に見たSF大作が何だったかによったりするじゃないですか。心を動かされるのは、やっぱり知らないことなんだと思うんです。すでに知っていることに出逢っても、「ああ、このパターンか」となってしまうから、大人になって自分の中のライブラリが増えるほど、感動の機会は減る気がするんですよね。だから、自分が経験しているからといって、「初めてそれを体験する人も常にいる」ということは考えるようにしています。
平澤
それは、音楽を作る時に思っているの?
中田
そうですね。
平澤
なるほど。確かにおっしゃる通り、知らなければ、それが最初の体験だもんね。
中田
そうなんです。
平澤
逆に、知ってしまっているからこそ、意識しすぎているのかもしれない。
中田
知識がいろんなものを作っているというか、例えば、今、何を格好いいと思えて、何をダサいと思うのかといったセンスも、知識とタイミングのバランスだったりすると思っていて。
平澤
多分、それは王子が若くて、進化し続けているからだという気がします。
中田
この考えは、割と最近、思い始めたことなんです。自分がつまらないと思う原因は、積み重ねてしまった曲の数だったりする、って。でも、自分がやったことがあることを、全ての人が同じように知っているわけではないな、と。例えば、僕が10年前にやってたけど、1年前にはやっていないことがあるとして、1年前からの僕しか知らない人は、10年前のことは知っていない。それを1年以内にやった別の人がいたら、僕の10年前はなくて、1年前の別の人がその人にとって最新なんですよね。だから、やっぱり「最初の人」っていうのは常にいるな、と。そのバランスの難しさを考えるようになったのかもしれないです。20歳になる前のあらゆることを新しく感じられる世代で曲を作っている人たちは、そもそもそんなこと考えもしないと思うし。この後もまた考え方がいろいろ変わっていくかもしれないけれど、今、すごく中間なのかな、という感覚はあります。
平澤
それはやっぱり、ずっと先端を走っているからだという気がします。進化の連続の中で、より高みに向かって進んでいく。その途中なのではないでしょうか。逆に、どうやって先端を走り続けて行くかを意識してしまったら、おじさんになる気がする。

中田
確かに。
平澤
未来に目を向けて、どういう作曲家になりたいとかありますか。
中田
日々、考えますけど、さまざまなメディアがある中で、自分が注目しているメディアが何かによって、成功のイメージはすごく違ってきますよね。テレビしか見ていない人にとっては、テレビに出ない人は活躍していない人、存在しない人じゃないですか。世界を見たら、うまくいっているチャンネルはもう本当にたくさんある。その中でどこを目指すのかも日々変化する。だから最近は、メディア軸で考えても仕方がないと思うようにどんどんなってきているんです。自分自身、どこかに拾われるコンテンツではありたいけれど、よりいい意味でアマチュアである感覚を忘れないようにした方がいいという想いがより強くなりましたね。
平澤
なるほどね。私よりも先輩の世代は、「売れる」ことは、レコードやCDが売れることとイコールだった。CDセールスにすごく縛られていた世代。でも、わかりやすかった。
中田
同じことを自分もやっていくんだなということが明確でしたよね。
平澤
そう。今は、「売れる」という価値観がどんどん変わっていて、答えがない。
中田
そうですね。
平澤
実は、それをどうしたらいいのかなと考えているのもフェイス・グループなんです。
中田
うんうんうん。
平澤
今、言われた通り、どこに向かうか、何を選んでもOKな時代の中で、CD販売やダウンロード数を増やしていくことも否定しないし、個人的には、どの方向に行けばいいか、あまり固定しない方がいいと思ってもいるんだけど、どうですか?
中田
そうですね。変えない部分としては、クリエイティブ的なマインドは固定したい。そこを固定させれば、逆に周りの選択肢が変わっていく感じですね。今は、どこを目指すかという外を固定して、マインドという中を変化させていくことはやらない方がいいと思っています。
理想とするクラブシーン。
平澤
先ほども話に出ましたけど、私が今、興味があるのは、実はクラブミュージックなんです。
中田
はい。
平澤
クラブには、場所があって、人がいて、音楽がある。そこだけなら固定できるかなという想いがある。特に日本は、それでも随分、遊べる場所は増えたけど世界から見ると遅れているでしょ。
中田
遊び場としてはそうですね。少ないというか、ちょっと違いますよね。
平澤
そういう現実、どう見ていますか。どう変えていったらいいかとか、考えはありますか。
中田
クラブが最初に登場した時は、ものすごく音楽に純粋な場だったと思うんですよね。「ディスコじゃなくてクラブだぞ」っていう時代。でも今、音楽に触れ合うという意味合い的には、クラブは実質ディスコに戻ったと思うんです。もちろんクラブとしてやっているところもありますけど、皆さんがイメージするクラブはディスコに近いと思うんです。クラブと一口に言っても、キャパシティ的に小さいものから大きいものまで幅がある中で、大きいクラブは大きなイベントができて、人もたくさん来るから古くて、小さなイベントは新しいことができているから格好いい、というイメージがあると思うんです。特に今、クラブに行っていない人にとってそのイメージは強いと思うんですけど、僕は逆なんじゃないかな、と思っています。大きなDJフェスとかに行っていない人は今の現場の感覚じゃなく、頭の中にはすごく古いEDM(エレクトロニック・ダンス・ミュージック)が鳴っている。でも実は、でっかい現場では次の音楽がかかっていて、小さなクラブには案の定の音楽がかかっている。今はそういう逆転が起こっていて、普通に定期的に行っておいた方がいいよねというクラブや、大きなところではできないことをやっているクラブの数が圧倒的に足りていない。今、まさに過渡期だと思うんです。

平澤
それは、どうしたら解決できるんだろう。空間の問題?それともDJの問題?
中田
なんだろうな。先輩がいるから行きたくない、っていう感じですね、多分。
平澤
どういう意味?
中田
自分たちの遊び場にするのに、先輩がいたら行きたくないじゃないですか。
平澤
なるほど。
中田
自分の先輩が全くいない中で、自分が今、この楽しい空間を作っている一人だという感覚が必要。楽しませてもらっているとか、何かを受けるというか、混ざる楽しみ方はもうできなくて、行きたくないという状況が増えちゃっている。
平澤
なるほど。わかるわかる。じゃあ、自分で何か作りたいと思ったりしている?
中田
そうですね。理想はありますね。ただ、お店としての理想ではなく、状況としての理想なので、お店として成立するかどうかはわからないですけど。
平澤
言える範囲で、どんな所が理想ですか。
中田
お店としていいという場合は、いつ行っても同じことやっている、中身が安定しているっていう意味が多いですよね。それがお店のバリューだったりする。僕としては、音楽的に、そこに行かなければ見たり聴いたり、体験できないようなことを常にやっているという空間が理想ですかね。DJって結構、空気をすごく読むというか、全体の8割以上は「この場ではこういう音楽をかけた方がいいだろう」という接客業のようなDJをしていますから。ミュージシャンの考えでは、そういうことはないと思うんです。
平澤
確かに。
中田
だから、かけたい曲があってもかけられないことが多い。もう少しミュージシャン寄りのことをいつでもできる場が増えたらいいな、と思います。
平澤
そうですね。
中田
ただそれをコントロールするにふさわしい、センスある人がすごく必要になってくる。この人なら、何をやらせてもバランス取れるという人。音楽サイトで言うところの、プレイリスト作っている人みたいな。だから才能がすごく必要。予定調和にならない人選ができて、そこに行けば、他では聴いたことがない曲が聴けるかも、そういう曲をかける奴がいるかも、というのを作りたい。しかも、小さいところでやっても意味がないから、ある程度、規模感のあるところで見ることができるようにしたい。それは出る人にとってもすごくチャンスになるので、そういうのが理想です。
平澤
やっぱりすごいアーティストだよね。感覚がすごくクリエイティブ。話していて、切り口が面白くて、いろんな気づきがあります。

「好き」の世界観が多様化するほど、
圧倒的なスターは絶対的な存在になる。
圧倒的なスターは絶対的な存在になる。
平澤
これからは、いわゆる「売れていくスタイル」ってどんどん変わっていきますよね。
中田
そうですね。例えば、YouTubeには、ホームビデオの動画も、大企業のオフィシャルプロモーションビデオも並行して上がっていますけど、音楽はその状況がもっと進んでいます。状況に差がないというか、プロモーションは違うかもしれないけれど、それ以外は一緒になってきていると思うんですよね。
平澤
ああ。
中田
従来は、実店舗でCDが面出しされているとか、「今週、この曲がこれだけ再生されました」という情報が重要だったりしたんですけど、コントロールの仕方がもうそこではないというか。今は、誰にとってもフラットな世界の話で、プロとアマチュアの差はどんどんなくなっていて、すでに「プロって何?」ということになってきている。全員自称かもしれないし、プロを目指すという言葉はもう死につつありますよね。
平澤
メジャーデビューとかね。
中田
そうです。僕の周りにいるトラックメイカー(音楽のバッキングトラックの制作者やインストゥルメンタル楽曲の作曲家・編曲家)の人たちと「今、それだけで食べていけるようになったのか」みたいな話をするんです。でも、世間の人からはプロだと思われている人も、ネットで人気がある人も、YouTuber的にそう思われている人もいて、それが本業なのか、副業なのかも曖昧だし、完全にここから先はプロだぞというものがなくなってきているなと感じますね。
平澤
本当にいろんな意味で境目がないよね。一定のレベル以上か、とか。
中田
本当に何も基準がないですよね。
平澤
そういうのって居心地いいですか。
中田
うーん。逆に基準がいっぱいありすぎて。
平澤
基準がいっぱいありすぎる?
中田
はい。「この人、すっごい有名だよね」というのが人によって違いすぎる。
平澤
ああ、確かに。小宇宙がいっぱいあるような。
中田
そうですね、はい。
平澤
例えば、昔は紅白とかレコ大を見ていたら、それが宇宙の全てのような感じがしていたけど、今は「好き」の世界観もみんなそれぞれ違っていて、いろんな宇宙がある。
中田
だから、圧倒的なものは、もう本当に圧倒的ですよね。「界隈のスター」はいっぱいいるけど、「誰もが知るスター」は、逆にもう絶対的に圧倒的。100万人ミュージシャンがいたら、上位10人くらいが全体の売上の99%を持って行く世界にどんどん近づいていると思うんですよ。
平澤
なるほど。目指すステージに立つことは、誰でもできるようになってきたけど、圧倒的な人は本当に一握りになり、その人たちが全ての世界。
中田
そうですね。みんな自分も小宇宙は作れるかもしれないって気づいていますよね。例えば、今は地下アイドルがいっぱいいますけど、それは、今は自分で勝手に言えるから。昔はアイドルって誰かが採用しなかったら成立しなかったものですよね。それってバンドと同じだと思うんですよ。高校生が「バンド組む?」みたいな感じで、「ちょっとやってみる?」っていう感覚。でも自主運営で面白いものは作れても、オーディションを勝ち取って、次の道筋が決まっていくというわけではない。だから小宇宙から出ていくのは難しいかもしれないですね。
平澤
ああ、確かにね。小宇宙の中でのトップにはなれる、自由に楽しめるけど、マスでトップになるのはより難しくなってくるかもしれない。
中田
そうですね。それぞれ宇宙が独立していて、全体としての輪がないんですよ。
平澤
確かに全てを内包する輪、大宇宙がない。
世界に向けて「これがJ-POPだ」を確立したい。
平澤
最後に、今、どんな夢を持っていますか?
中田
うーん。短い目標ではJ-POPを作りたいですね。僕、J-POPというジャンルはまだないと思っているんです。K-POPって、世界中の人が作曲に参加していますけど、どこを切っても統一されたもので攻める、この幅で皆やろうっていう枠組みが、結構、戦略としてあるような気がするんです。どう揃えているのかわからないですけど、ある程度、ここからここの範囲でやろう、みたいになっていて、差が開きすぎていない。日本にはその範囲がなくて自由すぎるから、「これがJ-POPだ」というものが一回もできていないと思うんです。

平澤
そういう意味でのJ-POPですね。
中田
そう。例えば、フレンチPOPも結構、変わってきていると思うんです。フレンチ・エレクトロもそうだけど、「今のフランスってこんな音楽です」って見えるじゃないですか。フランスの音楽も本来、すごいバリエーションがある中で、対国外に統一感を持たせて出しているというか。そういう意味でのJ-POPを作りたいと思っています。
平澤
確かにフレンチPOP、一つのジャンルとして確立できていますね。日本の作曲家って日本しか見ていない気がする。
中田
日本人が日本人の曲を聴く量がすごく多いからですね。だから、海外で何かやろうという人は、一人でやろうとする人しかいないというか。
平澤
ああ、なるほどね。
中田
僕、同じような曲を作っている者同士の仲が悪いのはすごく勿体無いことで、一緒に海外に出てツアーすればいいのに、と思うんですよ。DJの考え方では、同じ国で育った同じようなジャンルだったら、同盟組んでクルーとして世界中を回るじゃないですか。日本のミュージシャンにはそれがなくて、どっち派みたいなの作って戦っている。一緒にやればいいじゃん、っていうのが僕の考えです。
平澤
それ、作曲家、プロデューサーとして、実現できることはないの?
中田
僕自身が何か象徴になれるかどうかは置いておいて、そういう価値観に共感してくれそうな先輩はあまりいないですし、同世代にも少ないので、最初から説明されなくても「そうだと思っています」っていう世代と一緒にできたらいいなとは思います。
平澤
その発想、本当にすごく面白いね。今日は、初めてこうした話ができて楽しかったです。2020年の東京オリンピックの開催により、日本の音楽にも国際化の波が間違いなく押し寄せてきます。これまで以上に世界発信を続けてください。これからのご活躍を期待しています。
中田
僕こそ、すごく有意義な時間でした。
平澤
どうもありがとうございました。


中田ヤスタカさんプロフィール
2001年、自身のユニットCAPSULEにてデビュー。日本を代表するエレクトロシーンの立役者であり、Kawaiiダンスミュージックからハードなトラックまで、その独自の感性によって世界中のアーティストから支持を受けている数少ない日本人アーティスト。Madeon、Porter Robinson、Sophie(PC Music)など第一線で活躍中の彼らも「強くインスパイアされたアーティスト」として中田ヤスタカの名を挙げるなど、海外シーンへの影響力も大きい。国際的なセレモニーへの楽曲提供や、北陸新幹線金沢駅の発車予告音などパブリックな作品の他、ハリウッドを始めとする国内外数々の映画の楽曲制作にも携わり、映画スター・トレック イントゥ・ダークネスでは監督であるJ・J・エイブラムスと共同プロデュースによる劇中曲も手がけているなど、その活動の幅は多岐に渡る。音楽プロデューサーとしても、Perfume、きゃりーぱみゅぱみゅなど数々のアーティストを世に送り出している。